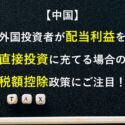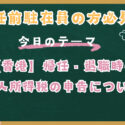中国法人の2025年度雇用コンプライアンスガイドライン~最高裁・広東省高級人民法院の労働争議典型事例を参考に~
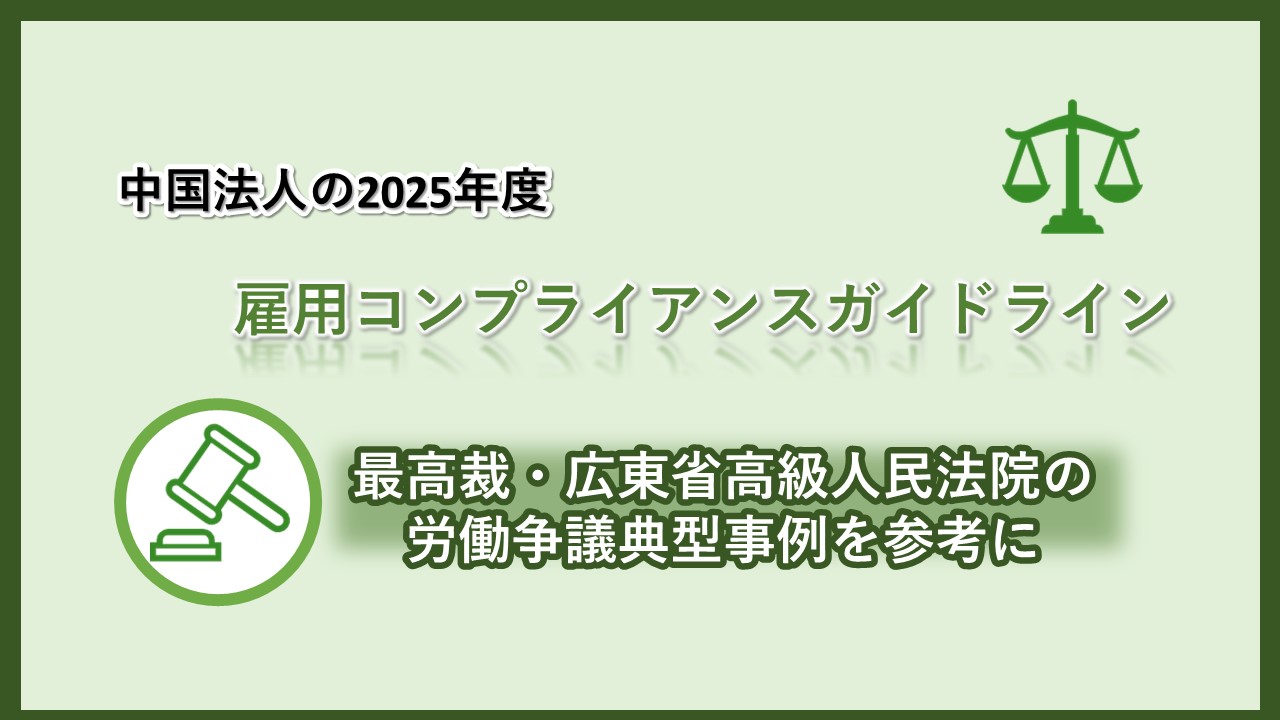
2025年5月1日「メーデー(労働者の日)」前夜、最高人民法院と広東省高級人民法院は相次いで労働争議典型事例を発表し、急速に変化する労働関係管理において明確な司法指針を提供した。これらの事例は、新業態雇用、解雇コンプライアンス、越境責任などのここ最近の問題に焦点を当てたもので、労働権益保障が新しい段階に入ったことを示している。
新しい裁判傾向
新業態「配車アプリやフードデリバリー事業」における労働関係の認定
『実態が形式より優先される』
当判例において、配車アプリ貨物ドライバーのA氏と雇用主の間では、労働契約が締結されていなかったが、裁判所は「支配的労働管理」の以下の三要素により労働関係が成立することを認定した。
- 運輸会社が配車と価格決定権を掌握している、
- 月次で楊某の主たる報酬を支払っている、
- 業務内容が会社の中核事業に属している。
また別の事案において、広東省の配達員と雇用主との間で『業務委託協議』が締結されていたが、実際には勤怠管理と賞罰管理を受けていたため、裁判所は実態としてその労働関係が存在していることを認定した。
裁判の論理が大きく転換
契約の名称はもはや決定的要素ではなく、『実態が形式より優先される』という原則が判断基準として確立された。裁判所は業務委託契約などの形式的な枠組みを超えて、
『指揮監督関係(人格的従属性)』
『報酬の労務対価性(経済的従属性)』
『組織への組み込み度(組織的従属性)』
という三要素を総合的に判断し、実質的な労働関係の有無を認定するようになった。
雇用自主権の境界~合理性審査が厳格化~
成都某科技会社の従業員が労働節に残業を拒否したことを無断欠勤とみなし解雇された事件で、裁判所は
「総合労働時間制を実施している場合でも、企業が法律で定められた休日に従業員に就業を命じた場合、それは時間外労働(残業)として扱われ、従業員は拒否権を有する。」
として、「法定休息権は剥奪不可」と明確に判定を下した。
従業員の配置転換・賃金変更に関する「4要素審査基準」
| 審査項目 | 判断基準 | 参考判例 |
| 経営必要性 | 客観的に、その業務調整が必要であるかどうか | 上海第二中級人民法院
職場変更無効判決 |
| 差別的取扱の禁止 | 特定個人に対する不利益な変更 | 南京中級人民法院事件
個別減給無効判決 |
| 労働条件の維持 | 福利厚生の不利益となる変更の禁止 | 南通中級人民法院事件
福利厚生の一方的な削減は無効判決 |
| 手続適正性 | 協商一致なしの契約変更は無効。 | 深圳中級人民法院事件
一方的な契約変更は無効判決 |
解雇権行使~「二段階審査」の定着~
解雇の有効性判断において、従来の単一的な行為審査*のほか、「就業規則の有効性+手続適正性」も判断要素に加わり、二段階審査が確立された。
| 山東省高級人民法院 | 労働者代表との協議プロセスを経ていない就業規則を解雇根拠とできない判断を示した。 |
| 新疆ウイグル自治区高級人民法院 | 労働組合への事前通知を欠く解雇を無効とする判断を示した。 |
| 深圳市中級人民法院 | 業務時間中の私的行為に対して「頻度・業務影響度」で重大性を判断 |
| 広州市中級人民法院 | 業務過誤(業務遂行中の過失や怠慢)への対応に対して「過失の程度と処分の均衡」を要求 |
*単一的な行為審査:雇用主の解雇行為の合法性を判断する際に、その解雇を直接引き起こした「特定の行為」(通常は労働者の過失や違反行為)に焦点を当て、その行為自体が解雇の正当な根拠となり得るかを審査する手法を指します。
越境雇用における責任所在
成都中級人民法院は、中国企業が海外子会社を通じて労働者のB氏を雇用した事案において、「対外請負工事管理条例」に基づき、多重下請け構造の大元となる中国の発注元を雇用主責任の主体と直接認定した。
また、広東省高級人民法院では別の事案において、越境雇用においては実際の勤務地、業務内容、サービス対象などの要素を総合的に考慮して責任主体を認定すべきと明確にした判定を下し、企業が越境組織構造を利用した責任逃れを防ぐべきと示した。
判例が示す労働雇用の実務指針
1. 内定取り消しの法的責任
成都のIT企業がD氏に内定通知を出した後、一方的に内定の撤回を行った。しかし、その時D氏は既に前職を辞職していた。
法院は、採用の内定は法的拘束力を有するとの判断を示し、企業に1万元の賠償を命じ、企業に対し採用プロセスの管理の厳格化を要求した。
ポイント:内定通知発行前に、社内の承認プロセスに変更の必要性がないかを確認の上完了させ、訴訟リスクを回避すること。
2. 就業規則の内容規制
某電子機器企業は、取引先に対する売掛金が回収不能になった場合、その販売担当者に対して30%を賠償する義務がある条項を就業規則に盛り込んでいた。しかし、裁判所はこの条項は無効であると判断し、企業経営の固有リスクを労働者へ転嫁するような条項は違法であることを明確にした。
ポイント:企業が民主的手続きを経て就業規則を制定した場合でも、その内容が「企業の法的責任の免除」または「労働者の権利排除」に該当する場合は無効となる。
3. デジタルプラットフォームの管理責任
南京中級人民法院は、配達プラットフォームの配達員に関する訴訟において、新たな判断基準を以下のように示した。
「プラットフォームがアルゴリズムに基づき、配達員に対して罰金・アカウントの停止を行う場合、具体的な違反事実と計算ロジックを明示しなければならない。違反した場合は、配達員の収入損失を補填する義務がある。」
重大な変化:プラットフォームはアルゴリズムの説明責任を負うことになり、これまで「ブラックボックス化」していた透明性の低いアルゴリズムの管理ではなく、「透明性のある」管理へ移行する必要がある。
企業向け労務リスク管理ガイド
1. フレキシブル雇用モデルの再構築
- 契約設計:労働契約ではなく、業務委託契約の場合は「固定労働時間」「強制ノルマ」など労働関係とみなされる特徴を表す条項を排除
- 管理区分:プラットフォーム企業(滴滴のような運転手と利用者を繋ぐプラットフォームを提供している企業)は、「基本ルール」(安全基準等)と「労働管理」(勤怠管理等)を明確に分離すること。安全基準は全員に一律適用可能だが、勤怠管理は労働関係が成立している従業員にのみ適用すべきである」
2. 解雇リスクを防止する制度の構築
- 制度点検:半年ごとに就業規則の民主手続きの記録と内容の合法性(特に懲戒条項)を法制度と照合して審査
- 事前審査:人事部(HR)→法務部→外部弁護士の3段階による解雇手続きのチェック体制を導入(山東の某企業ではこれより違法解雇紛争の72%減を実現)
3. 越境雇用の責任分離策
- 契約設計:中国本社が海外の現地雇用企業を通して雇用する場合において、それを監督する記録を保持(中国本社が実質的雇用者としての認定を回避)
- 保険対策:海外雇用企業より、派遣労働者のために「補充労災保険+商業責任保険」を加入(広東高裁判例で賠償リスク90%カバー可能)
4. AI管理の透明化改革
- 規約明示:配達員・ドライバー登録時にアルゴリズムによる罰則の具体例を条文化
- 異議申立:人工による再審査するチャネルを設置(南京のプラットフォームでこれよりアルゴリズム訴訟の65%減を実現)
5. 多元的保障システム
- 広東モデル:新規就業者向けに「職業傷害保険+商業保険」を併用(清遠の某飲食企業でこれよりリスクを100%カバー)
- 調停基金:人社局と法院の連携調停センターが労使紛争の90%を仲裁段階で解決(仏山事例)
まとめ
2025年の労働争議判例は、新しい業態による労働者の権利保護、企業の雇用の自主権の限界、解雇手続きの厳格化、越境雇用責任の明確化など、労働法務の重要なトレンドを示しています。特に、「実態が形式より優先される」原則の確立や、アルゴリズム管理の透明性が要求されることなど、企業のコンプライアンス対応がより複雑化しています。企業は、契約設計の見直し、内部規則の合法性チェック、越境雇用リスクの分散策などを通じて、法的リスクを最小化する必要があります。
当弁護士事務所では、労働法務に関する最新判例の分析から、企業向けコンプライアンス体制構築まで、総合的なサポートを提供しております。ご不明点や具体的なご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
本記事の目的:
本記事は、主に中国本土や香港へ進出されている、またはこれから進出を検討されている日系企業の皆様を対象に、中国本土や香港での経営活動や今後のビジネスに重大な影響を及ぼしうるような最新の法律法規と関連政策の主な内容とその影響、日系企業をはじめとする外資系企業の取るべき主な対策などを紹介することを目的として作成されています。
免責事項:
- 本資料はあくまでも参考用として作成されたものであり、法律や財務、税務などに関する詳細な説明事項や提案ではありません。
- 青葉コンサルティンググループ及びその傘下の関連会社は、本報告書における法律、法規及び関連政策の変化について追跡報告の義務を有するものではありません。
- 法律法規の解釈や特定政策の実務応用及びその影響は、それぞれのケースやその置かれている状況により大きく異なるため、お客様各社の状況に応じたアドバイスは、各種の有償業務にて承っております。
※当サイトの内容、テキスト、画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます。