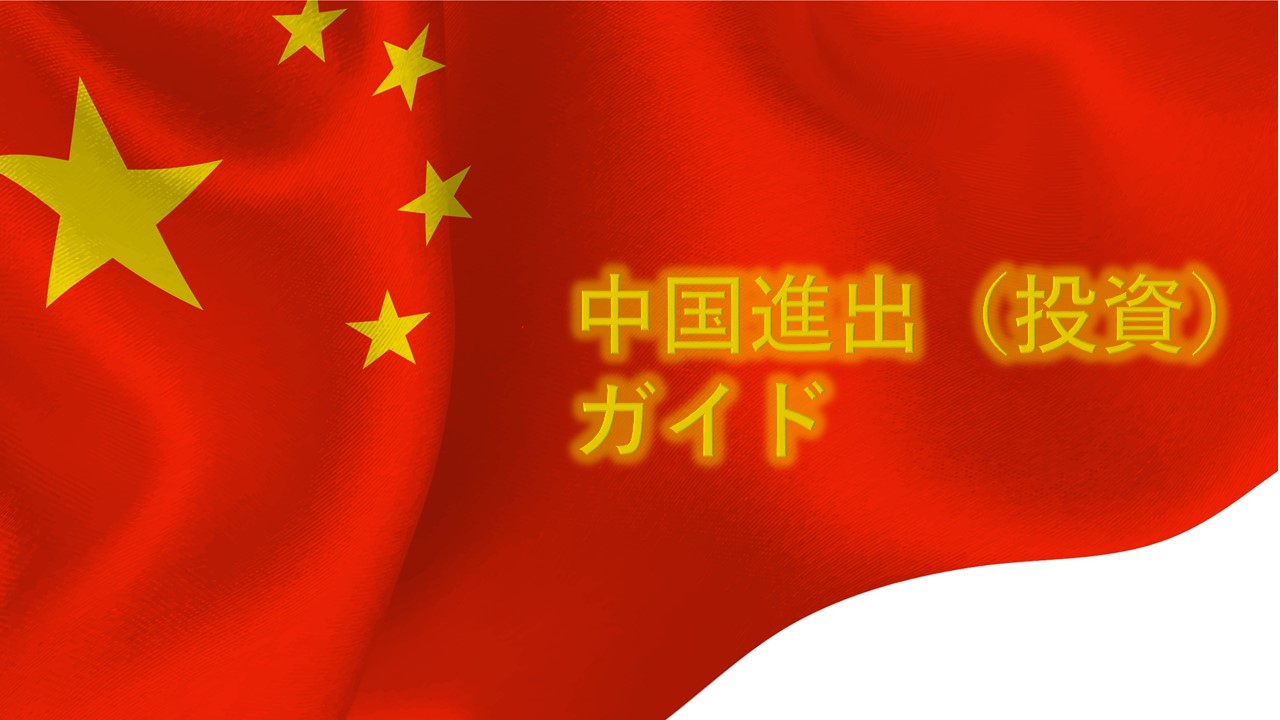中国進出(投資)ガイドブック
- 公開日 2020.12.30 最終更新日 2023.06.9 | 中国 資料 - ダウンロード
日系企業が中国本土へ進出する際の参考としていただくためのガイドブックを作成いたしました。
ハイライト:
- 中国投資のメリット
- 大湾区構想
- 優遇政策
- 近年の経済動向
- 保税区について
- 企業設立形態
- 業種別進出状況
- 投資総額と資本金について
- 国外配当について
- 中国税制について

当内容に関して何かご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
※免責事項:
- 本ページに記載されている情報はあくまでも参考を目的としており、法律や財務、税務などに関する詳細な説明や提案ではありません。
- 青葉グループ及び関連会社は、本内容における法律、法規及び関連政策の変化について追跡報告の義務を有するものではありません。
- 法律法規の解釈や特定政策の実務応用及びその影響は、それぞれのケースやその置かれている状況により大きく異なるため、その意思決定や行動を起こす場合は、事前に専門家へご相談ください。
※無断転載/引用禁止について:
当サイトが提供する情報、画像、音声等を、許可なく複製、転用、販売などの二次利用することを固く禁じます。掲載されている著作物に係る著作権・肖像権は特別の断り書きが無い限り、青葉ビジネスコンサルティングが保有します。