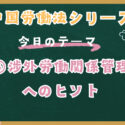【中国労働法シリーズ】最終回 – 違法な委託・下請け(外注)契約を根絶せよ
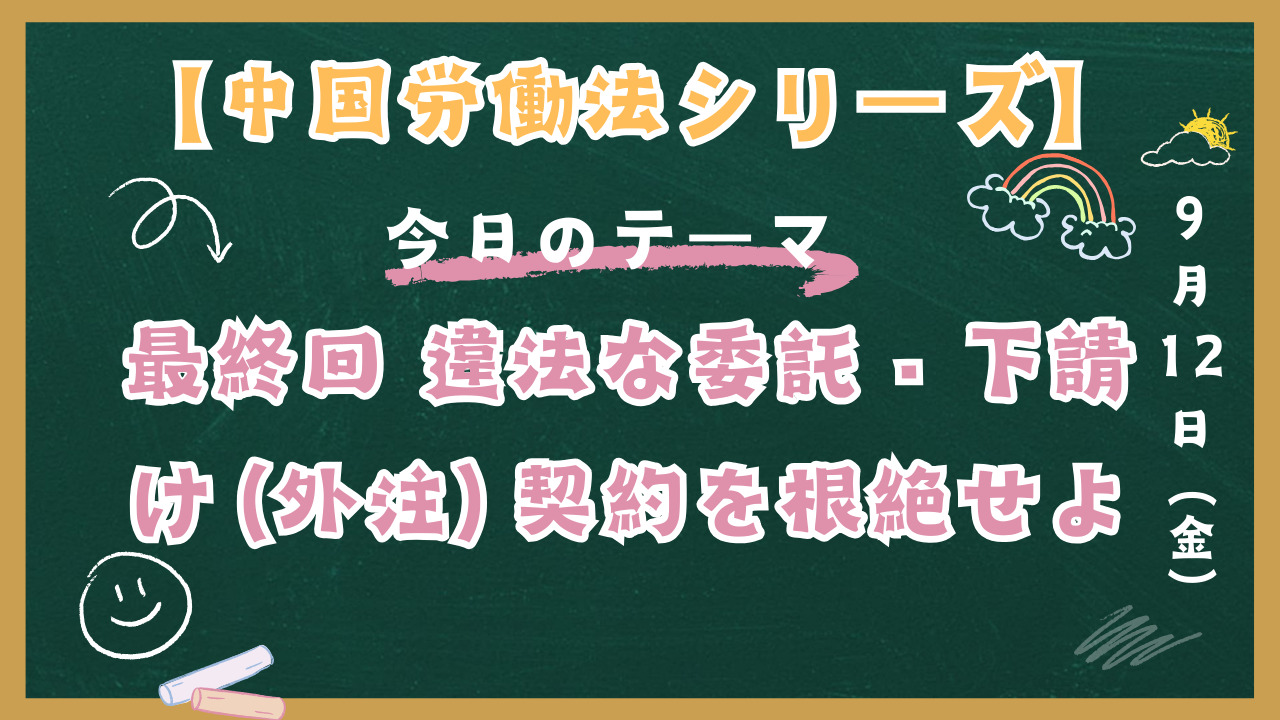
今年8月に中国最高人民裁判所より公布された「労働争議案件における法律適用に関する解釈(二)」(以下、「解釈」という)及び関連の典型判例に基づいて、5つのテーマに分けた記事を「労働法解説シリーズ」として、ご紹介させていただいております。
これまで第四弾まで発表してまいりましたが、今回は、本シリーズの最終回の記事として、「違法な委託・下請け(外注)契約を根絶せよ」と題しまして、雇用主が労災などの雇用責任を回避することを目的として、委託・下請け契約をしているという問題に一石を投じたケースについてご紹介いたします。
【過去記事:以下のリンクをクリックすると御覧いただけます。】
第一弾:【中国労働法シリーズ】①社会保険料の未納が与える衝撃とは?
第二弾:【中国労働法シリーズ】②労働契約が未締結であった場合に支払う、2倍賃金が免除される事由、明確に規定
第三弾:【中国労働法シリーズ】③競業避止義務の従業員への適用範囲が縮小
第四弾: 【中国労働法シリーズ】④ 涉外労働関係管理へのヒント
今回公布された「解釈」は、これまでの記事を御覧いただいて分かるように、企業の雇用管理に対しても新たかつより高い要求が提起された内容となっております。企業はこれに注目され、これら新規定に基づいて自らの雇用管理体制をアップデートする必要も出てくるかと存じます。本記事がその一助となれば幸いです。
Contents
一、使用者責任の徹底:違法な委託・下請け(外注)契約の根絶
この数年、一部の請負業者が雇用主としての雇用責任を回避するため、労働契約を直接作業員と結ぶのではなく、工事の請負業務の合法的な経営資格を持っていない組織や個人に再委託・下請けにだし、その委託先と作業員が労働契約を結ぶことで、雇用に関するリスクを下請け業者に転嫁させる事例が多く見受けられていました。
このような下請け業者の組織や個人の多くは、有事や労災が起きた際の法的責任を負担するための十分な能力もなかったため、このような状況において、労働者をどのように守るべきかという点が問題となっていました。そのため、「違法な委託・下請け契約」を根絶させ、雇用主の使用者責任を徹底させるため、今回、最高裁による労働争議に関する司法解釈の中で、業務の再委託または下請けに関する、以下の規定が公布されています。
【規定】
第一条 合法的な営業資格を有する請負業者が、その請負業務を合法的な営業資格を有しない組織または個人に再委託または下請けした場合、その組織または個人が雇用する労働者が、「労働関係上の責任主体」は当該請負業者であることの認定および、賃金の支払い、労働災害認定後の労働災害保険給付等の責任を果たすべきである、という請求を行ったときは、裁判所は法律に基づきこれを支持するものとする。
青葉の解説:
上記の規定により、労災が発生した際、労働者は社会保険行政部門に対し「労働災害の認定」と同時に「労働災害保険責任を負担しなければならないのは請負業者である」という認定についても申請することができます。
そして、この申請が認定された後は、本ケースの裁判結果のように、もし請負業者が労働者に対して労災保険料を納付していない場合であったとしても、労働者は請負業者に対して労災保険の待遇と同じ支払いを行ってもらうよう請求することができます。
またこれに加え、上記規定と類似していますが「使用者責任」としての以下の規則も確立されました。
- 合法的な請負業者が、業務を無資格の事業者や個人などに再委託する場合、その最終労働者である個人に対して労働報酬の支払い、労災保険の補償などに関する責任を負う必要がある。
- 無資格組織が資格を有する組織に名義を借りて営業を行う場合、名義貸しを受けた組織は同等の責任を負う。
本条2つの規定により、有資格となる請負業者の責任範囲を労働報酬の支払い及び労災認定後の労働災害保険待遇などにまで拡大したため、無資格の事業者へ委託・下請け契約を行ったとしても、労働者に対して、最終的な責任を負わなければならないことを意味しています。
これまで建築・製造・物流業界などに広く存在する「請負業者の農民工の雇用」という労働契約関係に対し「使用者責任」の規則が確立されたのは初めてのことで、責任を逃れるための中間業者の利用を根絶させる、という当局の姿勢がみてとれます。
二、典型的な判例
解釈とともに公布された、「違法な委託・下請け(外注)契約の根絶」に関わる典型的な判例をご紹介します。
【労働争議典型判例1】—ある建設会社とC氏の労災保険給付紛争事件
結論:資格のない再委託・下請け業者が雇用した労働者が労災と認定された場合、資格のある元請負業者が労災保険給付の支払責任を負う
【事案の基本的状況】
とある建設プロジェクトの元請け業者である建設会社(以下、同社という。)は、その工事の施工をR氏へ下請けに出しました。2021年8月、R氏はこの工事においてC氏を現場作業員として採用しました。またこの時、別の事案において、同社とC氏の間には労働関係が存在しない旨が判決されていました。そして2021年10月、C氏はこの工事の作業中に高いところから転落し負傷してしまいました。そして医者からは、腰椎(ようつい)骨折と診断されました。
そして2023年3月、人事部門社会保障課は、C氏へ「労災認定決定書」を発行し、C氏の負傷を労災と認定し、そして同社がC氏の労災に対して労災保険責任を負うようにとしました。また労働能力鑑定委員会は、C氏の労働機能障害の等級は8級で、日常生活の自立障害の等級は該当なし、そして休業保障期間は6ヶ月であることを確定させました。
そのためC氏は、人事部門社会保障課と労働能力鑑定委員会の結果をもって、労働争議仲裁委員会へ、同社に対して8級障害に該当する労災保険の待遇と同等の支払いを求める申請を行いました。労働人事争議仲裁委員会はC氏の請求を支持しましたが、同社はこの結果を不服として人民法院へ訴訟を起こしました。
【裁判結果】
状況として、建設会社は工事をR氏へ下請けにだし、R氏が雇用したC氏が工事の作業中に負傷しており、建設会社とC氏の間には直接的な労働関係は存在していないものの、依然として建設会社は本工事の請負業者として、労災保険責任を負う必要があるとしました。そして、建設会社がC氏のために労災保険料を納付していない場合は、C氏に労災保険の給付金に相当する金額を直接支払うよう判決を下しました。
裁判所は、『最高人民法院による労災保険行政事件の審理に係る若干の問題に関する規定』に基づき、労災保険責任の負担は、労働関係の存在を前提条件としないことを指摘し、そのため、建築工事が個人に下請けされた場合であったとしても、労災事故が発生したときは、労働者使用主体資格を有する請負業者が労働災害保険責任を負うべきであるとしています。
【判例解説】
今回の判例の背景は、この数年、一部の請負業者が雇用主としての雇用責任を回避するため、労働契約を直接作業員と結ぶのではなく、工事の請負業務の合法的な経営資格を持っていない組織や個人に再委託・下請けにだし、その委託先と作業員が労働契約を結ぶことで、雇用に関するリスクを下請け業者に転嫁させる事例が多く見受けられていました。
またこのような下請け業者の組織や個人の多くは、有事や労災が起きた際の法的責任を負担するための十分な能力を有していないことがほとんどといった状況でした。この状況において、労働者をどのように守るべきかという点が問題となっており、このような違法な再委託・下請けを根絶させ、雇用主としての責任を徹底させるため、今回、最高裁による労働争議に関する司法解釈の中で、業務の再委託または下請けに関する規定が以下の通り公布されました。
『最高人民法院による労災保険行政事件の審理に係る若干の問題に関する規定』第3条第1項の規定:
「社会保険行政部門が以下に例示する企業を労災事故の責任主体であると認定した場合、人民法院はこれを支持する……(四)雇用主が法律や法規の規定に違反して、請負業務を用工主体資格を有しない組織または自然人に請負業務を再委託し、当該組織あるいは自然人が受け入れて雇用した労働者が業務中に労災で死傷した場合、もともと労働者を雇用していた単位が労災事故の責任を負う。」
そのため、労災が発生した際、労働者は社会保険行政部門に対し、労働災害の認定と同時に、労働災害保険責任を負担しなければならないのは請負業者である、ということを認定してもらう申請ができます。
そして、労災が認定された後は、本ケースの裁判結果のように、もし請負業者が労働者に対して労災保険料を納付していないような場合であったとしても、労働者は請負業者に対して、労災保険の待遇と同じ支払いを行ってもらうよう請求することができます。
本件において、請負業者が労災保険待遇の支払い等を含む労働者使用主体としての責任を負うという規定は、違法な下請け・再委託行為に対する否定的な姿勢を表しており、また労働者が労災発生した際には、迅速な救済を受けることが出来る体制強化と、建築業界の秩序の健全化及び規範化を促進しさせ、労働者の合法的な権益を十分に保護するものであるといえます。
三、リスク軽減のための対策
この規定や判例を踏まえまして、実務上、企業が下請けや委託をする際の、リスクを低減するための対策が以下となります。
1. 下請け審査:
まず最初に委託先が合法的な営業資格を保有しているかどうかを審査し、資格がなければ契約をしないよう徹底することです。
仮に故意に雇用責任を回避するためではなくとも、その委託先が実は資格がない業者であった場合は、雇用した作業員の労災責任を負わなければならない可能性が高くなるため、必ず有資格業者であるかどうかについて確認する必要があります。
また契約時に資格があったとしても、それを失う場合もありますので、年次での審査が推奨されます。
2. 名義貸し禁止:
これは当然のことながら、外部の業者が自社を語って行う営業行為から発生するリスクを回避するためにその行為を禁止にします。
3. 雇用責任の明確化:
委託先が有資格である場合についても、労働者の雇用においてその責任について委託先が責任を負うのか、それとも元請け業者が負うのか、どの責任が誰に帰属にするかを書面に明記した上で、当事者の署名や捺印した確認書を準備しておく、ということになります。
これらは、企業が業務の再委託・下請けを行う際のリスクを避ける対策ですが、もし労働主体として責任を負う立場である場合は、労働者の労災保険の納付がなされているか、確認および徹底しておく必要があります。
最後のまとめ
「中国労働法シリーズ」としてご紹介した、『労働争議案件における法律適用に関する解釈(二)』に関する内容は、今回の第5弾を最後に終了となります。
最後に本件について一言でまとめると、「背後にある司法価値の新規転換」であると言えます。そして『解釈(二)』は、以下のような労働司法理念の深い変革を示しているとも言えます。
- 形式の平等から実質の公平へ:契約の外観に潜む実質的な雇用関係を見極める
- 個別救済から源流管理へ:判決ルールにより企業に予防メカニズムの構築を促す
- 放任型イノベーションからバランス点の模索へ:商業利益の保護と就業の自由の保障のバランスポイントを模索
労働法は、労働者の保護、企業行動の規範化、社会的な公平性と経済の調和ある発展の促進において、重要な役割を果たしています。前述の理由に基づいて、企業が回避ではなく法律で規定された権利と義務を厳格に遵守し、積極的に新規定の核心を管理基準へ転換すべきであると言えます。
中国は地域によって労働実務の運用が異なり、各地域の地方規定を確認することが極めて重要です。何かご懸念やご質問がございましたら、経験豊富な弁護士が在籍するAobaグループに、いつでもお気軽にお問い合わせください。
参考リンク先:
本記事の目的:
本記事は、主に中国本土や香港へ進出されている、またはこれから進出を検討されている日系企業の皆様を対象に、中国本土や香港での経営活動や今後のビジネスに重大な影響を及ぼしうるような最新の法律法規と関連政策の主な内容とその影響、日系企業をはじめとする外資系企業の取るべき主な対策などを紹介することを目的として作成されています。
免責事項:
- 本資料はあくまでも参考用として作成されたものであり、法律や財務、税務などに関する詳細な説明事項や提案ではありません。
- 青葉コンサルティンググループ及びその傘下の関連会社は、本報告書における法律、法規及び関連政策の変化について追跡報告の義務を有するものではありません。
- 法律法規の解釈や特定政策の実務応用及びその影響は、それぞれのケースやその置かれている状況により大きく異なるため、お客様各社の状況に応じたアドバイスは、各種の有償業務にて承っております。
※当サイトの内容、テキスト、画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます。